双子ママが解説!妊娠・出産費用の平均100万円をなるべく安く抑えるには?
[公開日]2018/01/09

妊娠から出産までの費用がどれくらいかかるのか、不安に感じていませんか?
妊娠中にどの病院にかかるのか、出産をどのような方法でするのか、里帰り出産をするのかによっても、妊娠から出産までにかかる費用も大きく変わりますし、住んでいる自治体の助成制度もそれぞれ違います。
特に助成制度は知らずに申請しそこねるともらうことができません。どんな制度があって、どんな手続きが必要なのかは事前調査が必要となります。
筆者は双子を出産した経験のあるママです。双子となると、妊娠から出産までの費用が通常よりも高額になりますが、助成制度を利用することで、かなり負担が楽になったので解説します。
目次
妊娠中に負担する費用はいくら?
赤ちゃんを授かるには本当におめでたいことですが、心配なのは負担する費用のことです。
待望の妊娠を心から喜べるように、妊娠中に負担する費用のことをしっかり把握しておきましょう。
助成金の確認が必要な妊婦健診費用
 妊娠したら定期的に受ける妊婦健診ですが、保険がきかないため実費負担になります。
妊娠したら定期的に受ける妊婦健診ですが、保険がきかないため実費負担になります。妊娠が順調にすすんだ場合、厚生労働省が推奨している妊婦健診は、以下の14回になります。
・妊娠初期〜23週まで……4週間に1回
・24週〜35週まで……2週間に1回
・36週目以降……1週間に1回
・24週〜35週まで……2週間に1回
・36週目以降……1週間に1回
しかし、母体や赤ちゃんの状態や、病院の方針によって回数は違ってきます。
ちなみに筆者のように双子などの多胎妊娠の場合は、健診の回数は約2倍になると考えておきましょう。
健診の費用は病院によってまちまちで、検査の内容によっても別に費用がかかったりしますが、大体の目安として1回3,000円〜1万円の範囲内です。
これがおよそ14回あるとして、全部で10万円前後が妊婦健診にかかる費用だと覚えておきましょう。
しかしながら、ほとんどの自治体で妊婦健診にかかる費用の助成があります。
厚生労働省によると、全国平均では妊婦検診1人当たりに98,834円が公費で賄われているので、手厚い自治体ならばほぼ負担がないことになります。お住まいの自治体がどのような助成を行っているか、調べておきましょう。
また、14回以上の通院となるため、遠方の病院にかかる場合は交通費のことも念頭に入れておきましょう。
月に1000円~5000円程度!赤ちゃんの発育に役立つ葉酸サプリの費用
妊活中からとる人も多い栄養素である「葉酸」ですが、妊婦にも赤ちゃんの健康な発育のためには葉酸が必要です。食事からとる葉酸に加えて、健康食品などに含まれる「モノグルタミン酸型の葉酸」をとることが重要で、厚生労働省でも推奨されています。
健康食品の中でも、手軽に飲みやすい「葉酸サプリ」を使って補給するのがおすすめです。
1,000円程度から5,000円以上のものまで、葉酸サプリの値段もさまざまですので、月額費用と継続できるかどうかを考えてどのサプリにするか決めましょう。葉酸サプリの比較記事を参考にしてください。
マタニティウェアの費用は平均2万円~5万円程度
お腹が一番大きくなる季節によって費用も変わってきますが、妊娠時にしか着られないものを最小限にする工夫が必要です。季節に関わらず必要なのは、インナーです。大きくなるバストやお腹や腰を守るためのマタニティショーツは専用のものを用意しましょう。
ブラ 3〜4枚
ショーツ 3〜4枚
パジャマ 1〜2枚
ウェアトップス 3〜4枚
ウェアボトムス 2枚
ショーツ 3〜4枚
パジャマ 1〜2枚
ウェアトップス 3〜4枚
ウェアボトムス 2枚
これだけでも揃えると平均で2万円〜5万円程度の費用がかかります。ただし、ウェアは手持ちのワンピースでも臨月まで着られますし、伸縮性のある生地のロングスカートもおすすめです。
筆者は切迫早産で妊娠5ヶ月目から入院生活となったため、お腹が大きくなってから外出することはほとんどなかったのですが、その代わりパジャマとインナーは上記より多めに揃えました。
パジャマは出産後の授乳がしやすいように、前開きのものがおすすめです。
ベビー用品は全部で2万円以上の費用がかかる
 赤ちゃんに必要なものを表にまとめてみました。
赤ちゃんに必要なものを表にまとめてみました。| ベビー用品名 | 必要最低枚数 | 最低単価 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 短肌着 | 3枚 | 500円〜 | 1500円〜 |
| コンビ肌着 | 3枚 | 1000円〜 | 3000円〜 |
| 長肌着 | 3枚 | 500円〜 | 1500円〜 |
| ロンパース ツーウェイオール | 5〜6枚 | 500円〜 | 3000円〜 |
| スタイ | 3〜4枚 | 200円〜 | 800円〜 |
| くつした | 2〜3足 | 200円〜 | 600円〜 |
| 紙おむつ 新生児サイズ | 1〜2パック | 1200円〜 | 2400円〜 |
| おしりふき | 2〜3パック | 300円〜 | 900円〜 |
| 哺乳瓶&乳首 | 2セット | 850円〜 | 1700円〜 |
| 粉ミルク | 1缶 | 1000円〜 | 1000円〜 |
| 清浄綿 | 2〜3パック | 700円〜 | 2100円〜 |
| 哺乳瓶消毒器 | 1個 | 1000円〜 | 1000円〜 |
| 沐浴用ガーゼ | 2〜3枚 | 200円〜 | 600円〜 |
| ベビーバス | 1個 | 1000円〜 | 1000円〜 |
| 湯温計 | 1個 | 400円〜 | 400円〜 |
| ベビーシャンプー(全身用) | 1本 | 500円〜 | 500円〜 |
| 赤ちゃん用綿棒 | 1パック | 200円〜 | 200円〜 |
| 赤ちゃん用爪切り | 1個 | 400円〜 | 400円〜 |
他にも必要とされているものはたくさんありますが、赤ちゃんのお世話をしている中で揃えていけば良いので、生まれる前に最低限必要なものを挙げました。
上記の分をすべて揃えると、2万円以上の費用がかかります。
また、生まれる季節によっても肌着の枚数や衣類は違ってきますので、出産予定日の季節をよく考慮して準備しましょう。
赤ちゃんを車に乗せる場合は、必ずチャイルドシートが必要になります。法律でチャイルドシートは6歳まで必要なので、新生児から6歳まで使えるものを選んだ方がお得です。
赤ちゃんの寝具は、筆者の場合は特に準備せず、大人用のものを代用しました。ただし、清潔にはしたかったので、シーツや掛け布団は新しい物を準備し、枕は清潔なバスタオルを敷いて代用しました。
赤ちゃんはすぐに大きくなるので、ベビーベッドやベビーラックはレンタルがお得で便利です。
不要になったらすぐに返却できるので、処分したり保管する場所にも困ることがありません。
母親・両親学級は自治体の無料のものに参加するのもよい
 大きく分けて、病院や産院が主催するもの、自治体が主催するもの、民間企業などが主催するものがあります。
大きく分けて、病院や産院が主催するもの、自治体が主催するもの、民間企業などが主催するものがあります。母親学級は妊娠週数によって3〜4回ほど行われるのが一般的ですが、主催しているところによってそれぞれ違いがあります。
両親学級は父親を中心とした育児体験が主な内容なので、土日開催が多く、ほとんどの場合1回で終わります。
自治体が主催するものには、無料のものもあります。事前の申込みが必要なので、予約の前に日時や料金、通う回数など確認してみましょう。
ちなみに母親・両親学級は不安がある人が受ければ良いもので、絶対に必要なものではありません。
筆者は23週で切迫流産のため入院したため、全く母親学級を受けませんでしたが、それが原因で出産育児に困ることはありませんでした。
妊婦健診のオプション検査の費用
オプション検査には、主に「羊水検査」「母体血清マーカーテスト」「新生出生前診断」の3つがあります。それぞれについて、内容と費用をまとめました。 羊水検査・・・羊水を直接採取して、胎児の染色体異常や遺伝子異常があるか診断。10〜20万円程度の費用負担が必要。
母体血清マーカーテスト・・・母体から少量の血液を採取し、成分濃度から胎児の染色体異常の有無を調べる。1〜2万円の費用負担が必要。
新生出生前診断・・・母体血清マーカーテストより精度が高く、血液採取だけで胎児の染色体異常が検出できる。約20万円の費用負担が必要。
母体血清マーカーテスト・・・母体から少量の血液を採取し、成分濃度から胎児の染色体異常の有無を調べる。1〜2万円の費用負担が必要。
新生出生前診断・・・母体血清マーカーテストより精度が高く、血液採取だけで胎児の染色体異常が検出できる。約20万円の費用負担が必要。
検査を受けるには条件や妊娠週数の関係もあるので、医師とよく相談の上、検査を受けてください。また、検査後の結果についてもよく説明を受けておくことをおすすめします。
妊娠中の習い事の費用はどれくらい?
妊婦を対象にした様々なレッスンがありますが、主なものとおよその費用についてご紹介します。マタニティヨガ・・・1回3,000円程度
 出産前後に呼吸に合わせて無理のないポーズをすることで、心と身体の安定を図る目的で行われます。
出産前後に呼吸に合わせて無理のないポーズをすることで、心と身体の安定を図る目的で行われます。多くはフリーパスや回数券といった支払い方がありますが、1回のレッスン代の相場は3000円が目安です。
マタニティスイミング・・・月会費6,000円~1万円+入会金、マタニティ水着代
水中の浮力を利用して負担がかからないように運動し、妊娠中の不快な症状や出産への体力作りに役立ちます。マタニティ水着を準備する必要があり、インナーと合わせて5000〜7000円前後かかります。
レッスン代は施設によって違いがありますが、入会金が5000〜1万円、月会費が6000〜1万円が多いです。
音楽教室・・・月会費5,000円~1万円
クラシック音楽で赤ちゃんの胎教にもいいとされているのが音楽教室です。お腹の中でも赤ちゃんは色んな音を聞いているので、一緒にリラックスできます。
ピアノやバイオリンなど、自分で弾くきっかけにもなります。特に運動をしないので、安静が必要な妊婦さんでも参加できます。
月の費用はピアノレッスンだと5000〜10000円が相場です。
分娩入院費の負担額は40万円前後!出産にかかる費用
ここまでは出産前の準備でしたが、いよいよ出産自体にかかる費用を算出していきます。分娩や入院費にいくらかかるのか、助成金で賄えるのかについて、詳しく見ていきましょう。
分娩・入院費
出産する場所や方法によってそれぞれ違いがありますので、比較してみました。総合病院・・・約40万円
 特に希望しない限り、4〜6人の大部屋になります。
特に希望しない限り、4〜6人の大部屋になります。同室になった人と友だちになれるメリットもありますが、不特定多数のお見舞い客が部屋に訪れることや、お風呂やトイレが遠いというデメリットもあります。
費用は普通の分娩入院で40万前後が相場です。個室を希望した場合は、差額ベッド代が発生します。
これは健康保険適応外なので完全に手出しになります。1日あたり6000円前後かかります。
個人病院(産院)・・・約50万円
豪華な食事やエステ付など、産院にもさまざまな特徴があります。費用の相場は約50万円程度ですが、待遇のよいところはその分費用が上がります。
ただし、双胎や早産の恐れがあるなど、希望しても産院では診てもらえない場合もあるので、定期健診の時に心配事が見つかったら、総合病院や周産期センターなど専門的な医療の整ったところへ転院することもあります。
助産院・自宅出産・・・約45万円
助産師が分娩のサポートをし、医療法できちんと定められた施設が助産院です。大きな違いは産婦人科医がいないことで、出産の際に医師免許が必要な医療行為を行うことができません。
自宅出産の場合も助産師にお願いすることになりますが、自宅でサポートしてくれる助産師を探さなければなりません。どちらも正常な妊娠経過、自然分娩ができることが条件になります。
費用は助産院は45万円程度で、あまり病院と変わりません。自宅出産は30〜50万円ですが、助産師の出張料金や交通費が加算されることがあります。
帝王切開・・・約60万円
 帝王切開にも予定のものと緊急のものがありますが、いずれにしても経膣分娩より入院日数が長くなるため、費用が高くなります。
帝王切開にも予定のものと緊急のものがありますが、いずれにしても経膣分娩より入院日数が長くなるため、費用が高くなります。主な内訳は以下の通りです。
・入院費
・新生児管理費
・分娩料
・産科医療保障制度
・新生児、母体の検査、投薬
・出生届、指導料
・保険診療
などで、約60万円近くかかります。・新生児管理費
・分娩料
・産科医療保障制度
・新生児、母体の検査、投薬
・出生届、指導料
・保険診療
帝王切開での平均入院日数は6〜10日で、個室を希望すれば差額ベッド代が別途かかってきます。
筆者は双胎の切迫早産で入院中から、前期破水して緊急帝王切開になりましたが、出産後は個室を希望したので入院総額は80万円程度になりました。
出産まで1ヶ月半入院していたので意外にかからなかったこと、助成金や高額医療費の適用で後から戻ってきたので大変助かりました。
里帰り出産の場合は交通費と生活費もチェック
実家と住んでいる場所の距離にもよりますが、意外にかかるのが交通費です。また、居住地でもらった妊婦健診の補助券は、県をまたぐと使えないことがほとんどですが、後日領主書を提出すれば返金してもらえます。
また、夫と別々に生活する期間にもよりますが、夫の生活費の相場は3〜4万円/月です。
実家にお世話になるので、生活費をいくらいれるのか、お礼を支払うのかは各家庭で色々でしょうが、2〜3万円/月を支払うことが多いです。
妊娠・出産費用をサポート!利用できる制度・補助金
妊娠・出産にはかなりのお金がかかることがわかります。しかし、下記のような制度や補助金を利用すれば、負担する費用がかなり抑えられますので、できる限り利用しましょう。
出産育児一時金
妊娠4ヶ月を過ぎると、赤ちゃん1人につき42万円が支給されます。双子であれば2人分もらえます。事前に申請しておけば、病院への入院費用に充てることができ、病院で手続きをしてくれるので便利です。
出産費貸付制度
全国健康保険協会による制度で、出産育児一時金が支給されるまでの費用貸付制度です。無利子で出産育児一時金の見込額8割まで借りることができます。高額医療費制度
帝王切開や妊娠中の治療などで高額な医療費がかかった場合、申請して払い戻してもらえる制度です。自己負担額が21,000円以上のものを合算することができますが、月初から月末までの1ヶ月ごとの請求で計算されるため、月のまたがったものはそれぞれの月で費用が算出されてしまいます。
高額医療費控除
1年間で10万円以上の医療費を支払ったことを確定申告時に税務署へ申告書を提出すると、所得税などが軽減されます。未熟児養育費制度
 出生時の体重が2000g以下、もしくは医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんの医療費を負担する制度です。
出生時の体重が2000g以下、もしくは医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんの医療費を負担する制度です。申請が必要なので、自治体に必要なものを確認して手続きをしましょう。
指定の療育医療機関での入院費や治療費は全額公費負担となります。筆者の息子たちも1099gと1227gという極低体重児の双子でしたが、出生後2ヶ月の入院・加療を受けましたがすべて公費負担でした。
後で送られてきた医療費のハガキを見たら、2人で2千万以上の医療費がかかっていて驚きました。
出産手当金
産休手当とも言われますが、出産のために会社を休み、尚且つその間の給与が支払われなかった場合に受け取ることができます。出生予定日の42日前と、出産翌日から56日までの間で仕事を休んだ期間が対象となり、1日あたりの手当金は、「標準報酬額÷30日×2/3」となります。
傷病手当金
切迫流産、妊娠悪阻で働けなくなった場合に給与の3分の2を受け取ることができます。当てはまる方は申請しましょう。育児休業給付金
雇用保険に加入している
育休中に給料の8割以上が支払われていない
育休前の2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下
育休中に給料の8割以上が支払われていない
育休前の2年間に月11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
就業している日数が各支給単位期間ごとに10日以下
これらの条件を満たしていればパートや契約社員でも、育児休業給付金が受け取れます。
育休開始から180日までは給与の67%、それ以降から育休最終日まで50%が支給金額となります。
失業給付金
妊娠を機に仕事を辞め、再就職したいと考えている人が、失業給付金の延長を行うことができます。再就職活動を行う意志と行動があるが、失業状態にあることが条件で、退職する前の2年間に雇用保険に12ヶ月以上加入している必要があります。
退職の理由が妊娠・出産なら、最長で受給期間を3年間延長できるため、産後働くつもりなら申請しておきましょう。
ただし、退職して31日目から1ヶ月以内に管轄のハローワークに申請する必要があるので、注意が必要です。
医療保険
事前に医療保険に加入しておく必要がありますが、正常分娩以外での出産には、入院給付金や手術給付金を受け取れる場合があります。加入している医療保険があれば、よく契約内容を読み、保険会社に連絡してみましょう。
医療保険に入るなら妊娠前に!
妊娠中でも出産後でも保険に加入することはできます。しかし、妊娠や出産後に新規保険加入する場合、子宮部位に関わる疾病の不担保や出産に関わる疾病の不担保といった"条件つき"となってしまうことがほとんどです。
妊娠前に医療保険に入っておけば、通常分娩以外の疾病や手術、入院などに保険がおりることもあります。医療保険に入るなら、妊娠前に入っておきましょう。
筆者も妊娠前から加入していた医療保険のおかげで、入院費のうち差額ベッド代が補えました。しかし、妊娠後に他の医療保険に加入する際、帝王切開や婦人科系での疾病は不担保といった条件付きになりました。
出産祝い金
全国約20カ所の自治体で出産祝い金制度があります。交付金は、第一子で5万円、第三子では100万円と高額になる自治体もあります。
お住まいの自治体に、出産祝い金制度があるか調べてみましょう。
申請しないと損!費用負担を助ける出生届提出と同時にすべき手続き
赤ちゃんが生まれたら、出生届を必ず提出しますが、一緒にやっておきたい手続きがあります。
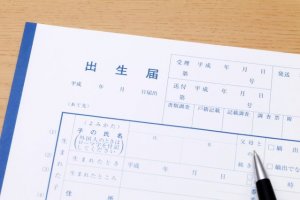
健康保険への加入
生まれたらすぐに両親どちらかの扶養として健康保険に加入しなければなりません。年収が多い親の扶養に入るのが普通ですが、父側に入ることが多いです。
扶養者が雇用されているなら、勤務先から手続きを行います。自営業などで国民健康保険なら、そちらで申請します。
乳幼児医療費助成制度
各市町村が行っている制度で、手続きをすれば医療費のが無料もしくは減額されます。自治体によって助成される子どもの年齢上限が違ったり、親の所得制限があったりするので、お住まいの自治体に確認しましょう。
児童手当
行政から支給されるもので、0歳から中学卒業まで受け取れます。子どもの年齢や数、また所得によって支給額が変わります。0歳〜3歳未満は15000円、3歳〜小学校修了前まで10000円(第三子以降は15000円)、中学生は10000円となります。
児童扶養手当
ひとり親家庭で支給されます。所得によって支給額がかわりますが、全部支給の場合は42290円/月、2人目は9900円加算、3人目以上は5990円の加算となります。
どの手続きも地域の役所で一度に手続きできますので、忘れないように済ませましょう。
1歳までは行事が目白押し!産後にかかる費用
赤ちゃんが生まれて育児に大変な時期ですが、産後にもいろいろとお金がかかることがあります。大切な家族の一員となった赤ちゃんのため、しっかり計画を立てていきましょう。
内祝い
出産時に親戚や友人から出産祝いをいただきます。お返しとして「内祝い」を送るのが慣わしですが、相場は「いただいた金額の半分」です。きちんと誰にどれだけいただいたかを把握して、失礼のないようにお返しをしましょう。
行事費
出産から1年目は子どもの行事が目白押しです。それぞれ費用の目安をご紹介します。お宮参り
 生後1ヶ月を無事に迎えたことを産土神に報告するのがお宮参りです。まずかかる費用はお参りする神社へ納める「初穂料」があります。神社によって違いますが相場は5000〜1万円程度です。また、赤ちゃんに着せる着物やベビードレスは3〜5万円が相場です。レンタルなら1〜2万円で抑えられます。
生後1ヶ月を無事に迎えたことを産土神に報告するのがお宮参りです。まずかかる費用はお参りする神社へ納める「初穂料」があります。神社によって違いますが相場は5000〜1万円程度です。また、赤ちゃんに着せる着物やベビードレスは3〜5万円が相場です。レンタルなら1〜2万円で抑えられます。両家の両親も参加した場合、お宮参り後に食事会をすることも多いですが、1人あたり3000〜8000円と考えておくとよいでしょう。
お食い初め
生後100日で赤ちゃんが初めて母乳やミルク以外のものを口にする行事です。一生食べ物に困らないように、健やかに育つようにという願いが込められています。準備するのは祝い膳と赤ちゃんの食器です。食器は漆器で揃えると2万円前後しますが、プラスチックの和食器ならは3000〜5000円前後です。祝い膳は1人あたり5000〜8000円が相場です。ホテルや割烹などでは1万円/1人程度かかることもあります。
初節句
 生まれてから初めて迎える初節句は、盛大にお祝いします。
生まれてから初めて迎える初節句は、盛大にお祝いします。男の子なら5月5日の端午の節句に五月人形や鯉のぼりを飾り、女の子なら3月3日の桃の節句にひな人形を飾ります。
お値段もピンからキリまで様々ですが、人気の価格帯は5〜20万円くらいのものです。
最近は住宅事情によって鯉のぼりが立てられなかったり、段飾りのひな人形が飾れなかったりしますので、無理のない範囲でお祝いしましょう。
この他に、親の衣服にも意外にお金がかかります。子どもの準備に一生懸命で当日まで自分の着るもののことを忘れていたということもあるので、予算をしっかり組んで準備しましょう。
出産費用は100万円前後かかるが半額以上を助成金で賄える
妊娠から出産まで、100万円程度かかります。そんなにお金がかかるのかと驚きますが、実は助成金や制度によってかなり手出しの金額は抑えられます。
自分が受けられる助成制度をしっかり把握して、申請の必要なものは期間内にきっちり申請しましょう。先に手出しの必要なものもありますが、後で戻ってくる、または遅れて支給されるものもあるので、トータルで見ると案外手出しは少なくて済みます。
まったく貯金などなかった筆者でも、双子の妊娠、長期の入院、帝王切開による出産、赤ちゃんたちのNICU入院という難局を乗り切れたので、お金に関して心配しすぎないようにしましょう。
